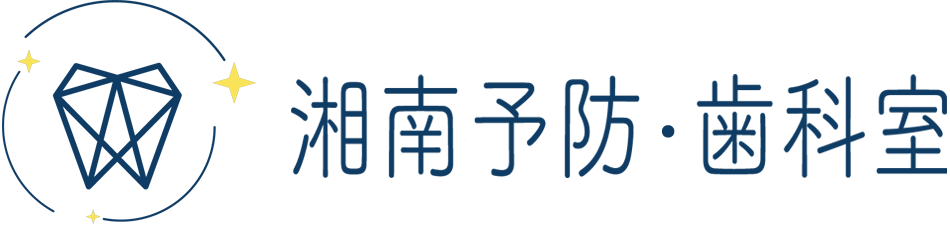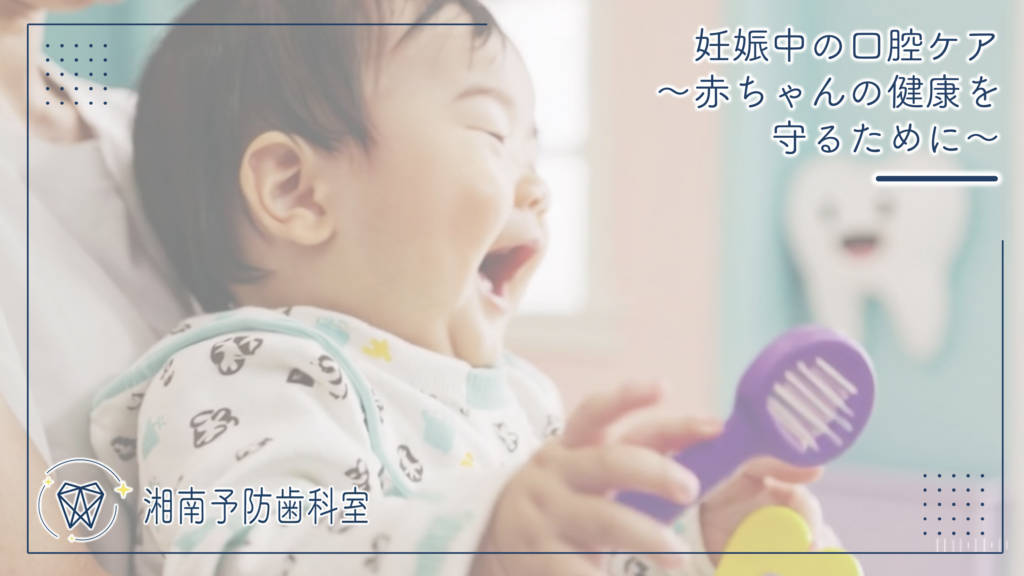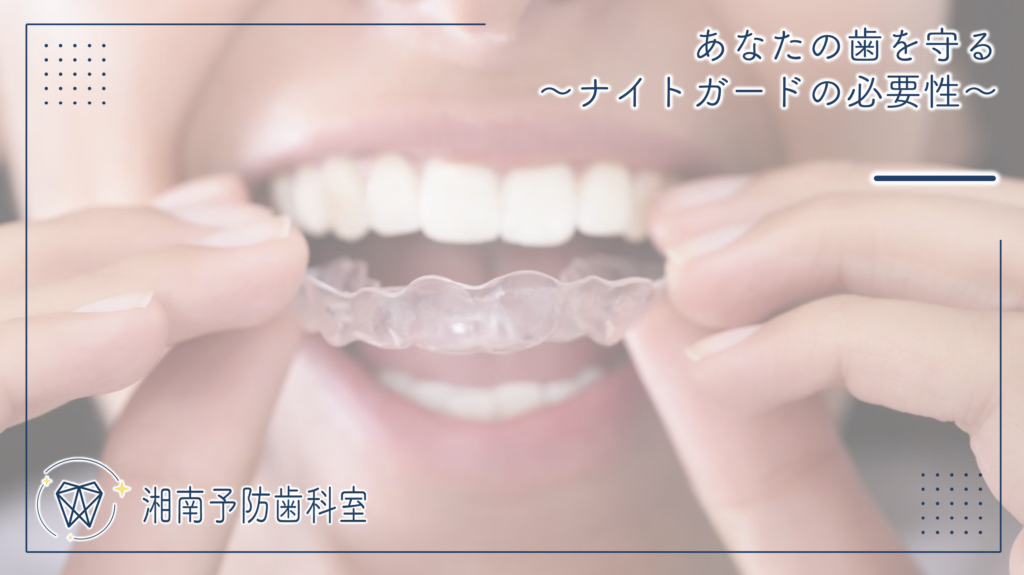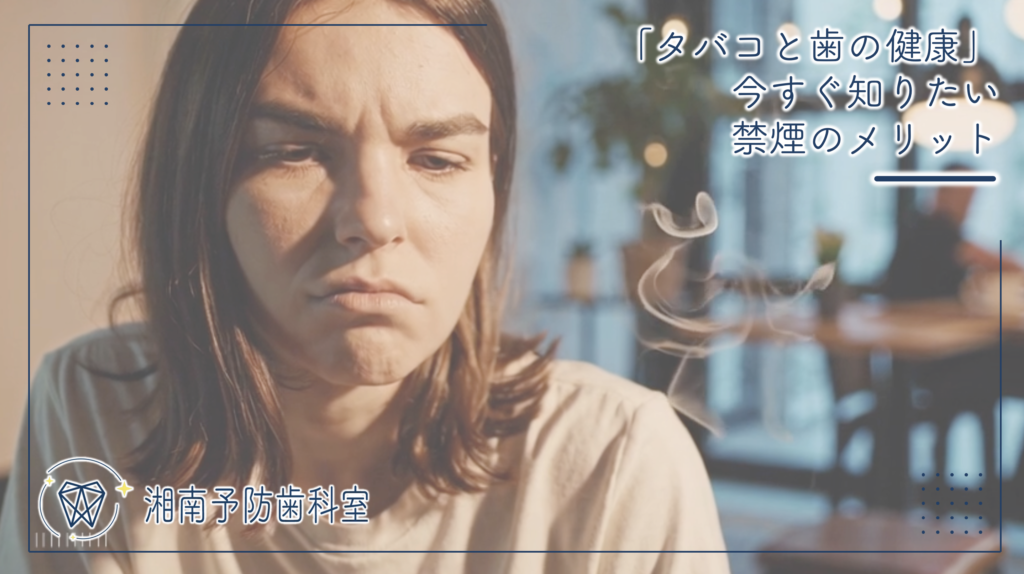こんにちは!湘南で口の中を守りたい気持ちNo.1の湘南予防・歯科室です
年齢を重ねると、歯茎が下がったり、むし歯や歯周病が進んだりするリスクが高まります。
しかし、「もう歳だから仕方ない」と諦めるのはまだ早い!湘南予防・歯科室はどんな状態でも歯を残して美味しくご飯が食べられることを諦めません!
予防歯科をしっかり活用すれば、シニア世代でも歯を長く保つことは十分可能です。
この記事では、シニア世代ならではの口腔トラブルや、歯を失わないための秘訣を詳しく解説します。
目次
内容
1. シニア世代に多い口腔トラブル
● 歯周病の進行
加齢とともに歯茎が下がる、骨が痩せるなどの変化で、
歯周病が進みやすくなることがあります。
● むし歯の再発
以前治療した部分が二次むし歯となって再発するケースが増加。
● ドライマウス(口腔乾燥症)
唾液量が減って自浄作用が落ちるため、むし歯や口臭、歯周病が悪化しやすくなります。
2. 歯を失わないための予防法とは?
● 歯周ポケットのケア
歯周病を予防・進行させないためには、歯と歯茎の境目(歯周ポケット)のプラーク除去が必須。
● むし歯リスクの管理
フッ素や唾液の力を上手に使いながら、こまめなケアでむし歯菌を抑制しましょう。
● 生活習慣の見直し
食生活や喫煙習慣などが、口腔環境に大きく影響します。
バランスの良い食事や禁煙を心がけることで、全身の健康にも良い効果が期待できます。
3. 定期検診で早期発見・早期対応
シニア世代こそ、定期的な歯科検診が欠かせません。
むし歯や歯周病は、初期段階で発見・治療すれば大きなトラブルを未然に防げます。
例えば、かぶせ物の隙間から始まるむし歯や、軽度の歯周炎なども、
早めに対応すれば歯を守れる可能性が高まるのです。
4. 自分でできるセルフケアのポイント
- 正しいブラッシング:
歯茎との境目や奥歯の裏側など、磨き残しが多い部分を意識して丁寧に。 - フロスや歯間ブラシの活用:
歯と歯の間にプラークが溜まりやすいので、補助清掃用具を取り入れましょう。 - 保湿の工夫:
ドライマウスが気になる方は、こまめな水分補給や口腔保湿ジェルなどを活用してみてください。
まとめ
年齢を重ねるほど、むし歯や歯周病のリスクは高まります。
しかし、シニア世代でも定期的なケアと予防を行えば、歯を失わずに過ごすことは十分可能。
湘南予防・歯科室では、一人ひとりの口腔環境に合わせたオーダーメイドの予防計画を提案しています。
「歯を守りたい」「いつまでも自分の歯で食事を楽しみたい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
笑顔あふれるシニアライフのために、一緒に歯の健康を守っていきましょう!
湘南予防・歯科室 院長 坪川 正樹
日付: 2025年10月1日 カテゴリ:医院ブログ