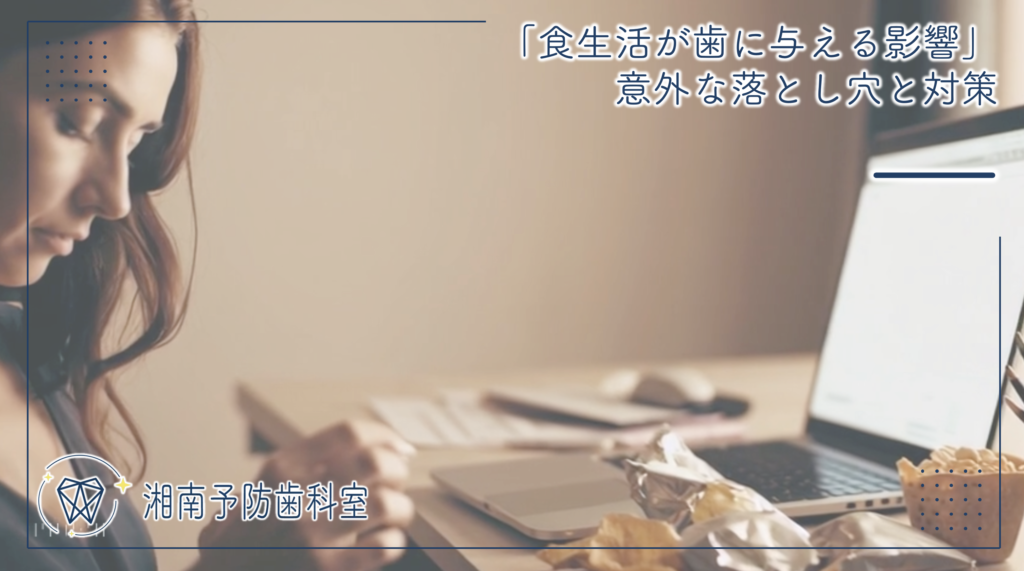
こんにちは!
湘南で口の中を守りたい気持ちNo.1の湘南予防・歯科室です
「食生活が歯に与える影響」意外な落とし穴と対策
毎日の食生活、実は歯の健康に大きく関わっていることをご存じですか?
むし歯や歯周病などを予防するには、適切な食習慣を知ることが欠かせません。
「甘いもの」を食べた時だけ歯が溶けるわけではなく、糖質であればどんなものであっても
むし歯菌が利用して歯を溶かすことがあるのです。
今回は、食生活が歯に与える影響と、その対策をわかりやすく解説します。
目次
内容
1. 食生活と歯の関係とは?
食べ物や飲み物を口にすると、酸が発生して歯の表面が溶けかける(脱灰)状態になります。
しかし、唾液の力によって再石灰化が起こり、歯は自然に修復される仕組みを持っているんです。
問題は、「脱灰の時間」が長すぎると歯が溶けたまま進行してしまうこと。
食習慣によっては、むし歯や歯周病リスクが高まる原因となります。
2. 甘いものだけじゃない!糖質全般に注意
甘いお菓子やジュースが歯を溶かすイメージは強いですよね。
しかし、「糖質」であれば何でも、むし歯菌のエサになります。
たとえば、牛乳やご飯など、いわゆる「甘くない」ものでも
糖質が含まれていれば、口の中を溶けやすい状態に導く可能性があります。
唾液検査では、「食生活のタイミング」や「糖質摂取の頻度」をチェックして、
いつ・どれくらい糖質をとっているかを把握することで、むし歯リスクを低減させるのです。
3. 意外な落とし穴:酸性食品の影響
「甘いもの=むし歯の原因」はよく知られていますが、酸性の強い飲食物にも要注意。
炭酸飲料・スポーツドリンク・柑橘類などを頻繁に摂取すると、歯の表面が酸で溶けやすい状態が続き、
エナメル質が弱る“酸蝕症(さんしょくしょう)”を引き起こすことも。
酸味のあるものを取った後は、うがいや水を飲むだけでも、口の中の酸を洗い流す効果があります。
4. 間食のとり方を見直そう
食事や間食の回数が多いと、酸性状態が長く続くことになります。
例えば、こまめにおやつをつまんだり、甘い飲み物をダラダラ飲んだりしていると、唾液の再石灰化が十分に追いつかないのです。
- 間食回数を減らす
- 甘い飲み物は一度に飲み切る(長時間チビチビ飲まない)
- 間食後にはうがいや歯磨き
こうしたポイントを押さえて、むし歯リスクを下げましょう。
5. バランスの良い食事と唾液パワー
歯を構成するカルシウムやリン、
再石灰化を促進する唾液の分泌をスムーズにするタンパク質など、栄養バランスが大切です。
硬めの食材(野菜や海藻など)をよく噛むことで、唾液の分泌も促されて歯や歯茎に刺激を与えます。
結果、自然なクリーニング効果や歯肉の活性化にもつながります。
また、糖質の摂り方を工夫し、タイミングや頻度を意識することで、むし歯のリスクを抑え、
唾液がもつパワー(緩衝能・自浄作用・免疫作用)を最大限に活かすことができます。
6. まとめ
食生活が歯に与える影響は、甘いお菓子だけが原因とは限りません。
牛乳やご飯などの「甘く感じない糖質」も、むし歯菌のエサになることがあります。
さらに酸性食品や間食の頻度、食べ方・飲み方のタイミングにも注意が必要です。
その対策として、間食回数を減らす・水やうがいを活用する・バランスの良い食事などを心がけてみましょう。
湘南予防・歯科室では、一人ひとりの食習慣や唾液検査の結果をもとに、最適な予防アドバイスを行っています。
ぜひ、お気軽にご相談くださいね。
湘南予防・歯科室 院長 坪川 正樹

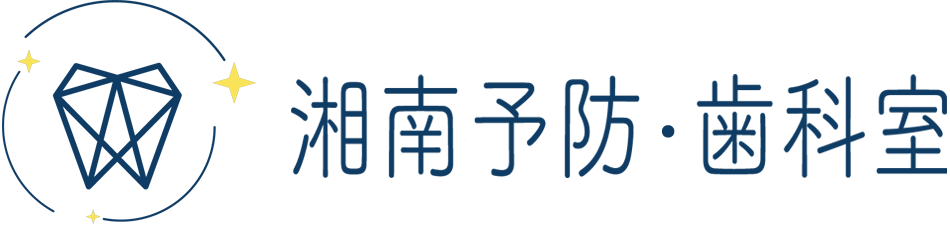

 こんにちは!
こんにちは!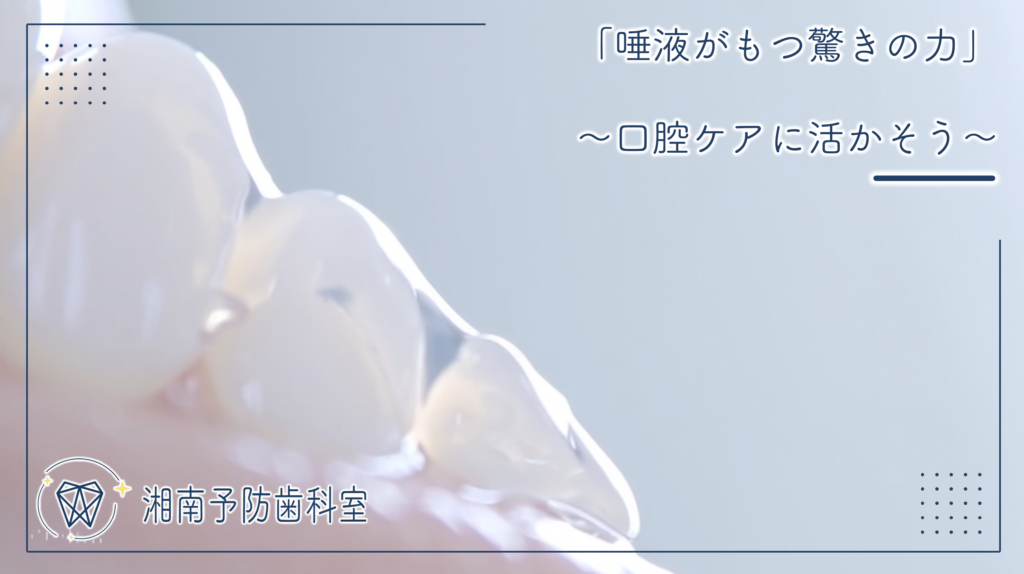 こんにちは!
こんにちは!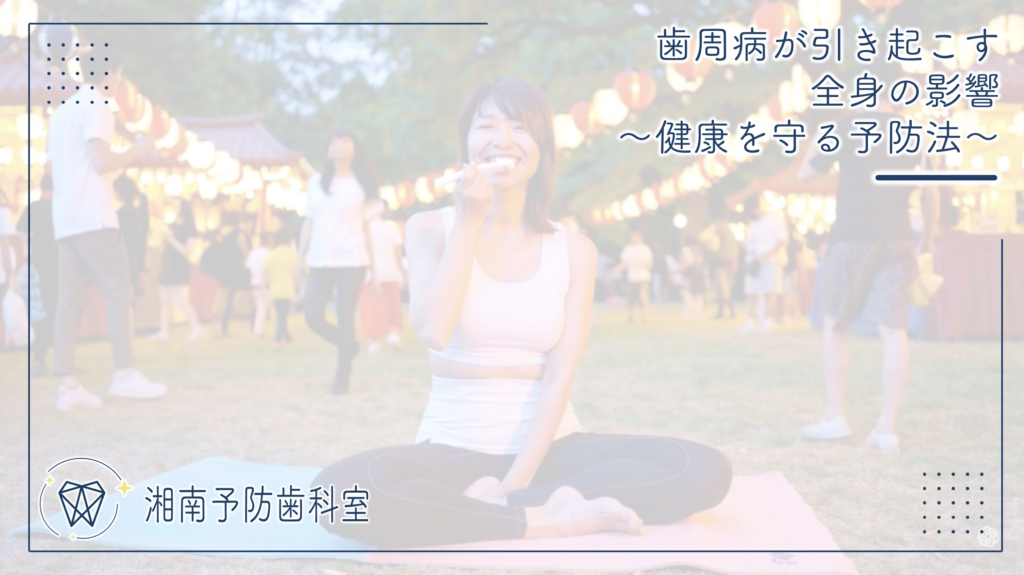 こんにちは!
こんにちは! こんにちは!
こんにちは!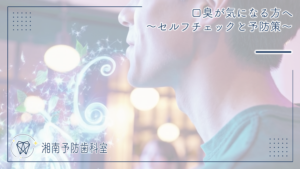 こんにちは!
こんにちは!