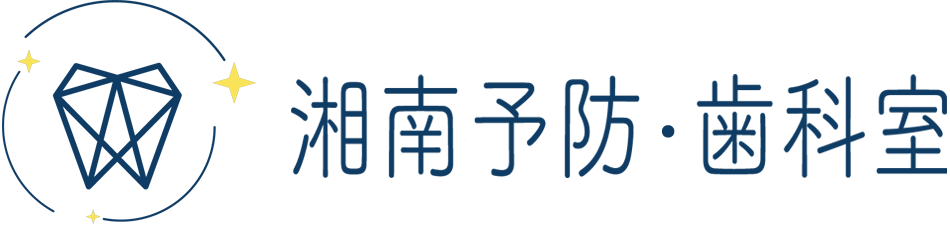こんにちは!
こんにちは!
湘南で口の中を守りたい気持ちNo.1の湘南予防・歯科室です
「あの時、甘いものを食べてそのまま寝てしまったから…」というように、
一瞬の出来事でむし歯ができると思われている方が意外と多いんです。
しかし、実際のお口の中はそんなに弱くありません。
歯は常に“溶ける(脱灰)”と“再び強くなる(再石灰化)”を繰り返しているのです。
それでもむし歯になってしまうのは、“溶ける”ほうにバランスが傾き続けるから。
今回は、そのリスク要因や仕組みを分かりやすく解説します。
目次
- 1. 歯は常に溶けたり強くなったりを繰り返す?
- 2. なぜ一瞬ではむし歯になりにくいの?
- 3. むし歯ができる仕組み~バランスが崩れるとき~
- 4. 実際にどんなリスクがある?
- 5. リスク要因を知って予防をはじめよう
内容
1. 歯は常に溶けたり強くなったりを繰り返す?
むし歯というと、“一度溶けたらもう終わり” というイメージがあるかもしれませんが、
実は歯のエナメル質は脱灰(溶ける)と再石灰化(強くなる)を
日々繰り返しています。
食事などによって酸が発生すると脱灰が進みますが、唾液の働きなどで
再石灰化が起こり、自然に元へ戻ろうとする力が働くのです。
2. なぜ一瞬ではむし歯になりにくいの?
甘いものを食べたり、歯を磨かずに寝てしまったりという“一瞬の出来事”で
すぐに大きな穴が開くわけではありません。
なぜなら歯には、自ら回復しようとするチカラが備わっているから。
一時的に酸が強まっても、再石灰化がしっかり働けばむし歯は防がれることが多いのです。
つまり、“少しずつ溶ける方へ傾く状態”が長く続くことが問題なんですね。
3. むし歯ができる仕組み~バランスが崩れるとき~
歯が脱灰と再石灰化を繰り返す中で、酸の影響が強い時間が増えたり、
唾液の量や質が低下したりすると、再石灰化が追いつかなくなります。
その結果、“溶ける方”が優勢になり続けると
むし歯として穴が開いていくわけです。
これが、むし歯が少しずつ進んでいく仕組みと言えます。
4. 実際にどんなリスクがある?
- 頻繁な間食:
何度も糖分(酸のもと)を取ると、再石灰化が間に合わず脱灰が進みやすい。 - 唾液量の減少:
加齢・ストレス・薬の副作用などによって唾液が少ないと、自然回復が追いつきにくい。 - 不適切なブラッシング:
プラークがたまり、菌が酸を産生しやすい環境に。
特に歯と歯の間はむし歯リスクが高い。 - 食生活の偏り:
栄養バランスが乱れると、歯や唾液の健康に影響が出やすい。
5. リスク要因を知って予防をはじめよう
むし歯は“突然できる”というより、“少しずつ溶ける方へ傾く状態”が続く結果です。
頻繁な間食や唾液量の低下、磨き残しや歯並びなど、
自分に潜むリスクを把握して対策を講じれば、むし歯の予防はぐっと進みます。
湘南予防・歯科室では、一人ひとりに合ったリスク管理やブラッシング指導をしています。
気になる方はぜひご相談くださいね😊。
まとめ
むし歯は、「あの時甘いものを食べて寝ちゃったから」という
一瞬の出来事だけで急に大きくなるわけではありません。
歯はもともと回復力があり、溶けたり強くなったりを繰り返しています。
ただし、溶ける力>強くなる力が長く続いてしまうと、
むし歯が進行してしまうのです。
日ごろの習慣を見直し、脱灰と再石灰化のバランスを整えることで、
むし歯リスクをぐっと下げることができますよ。